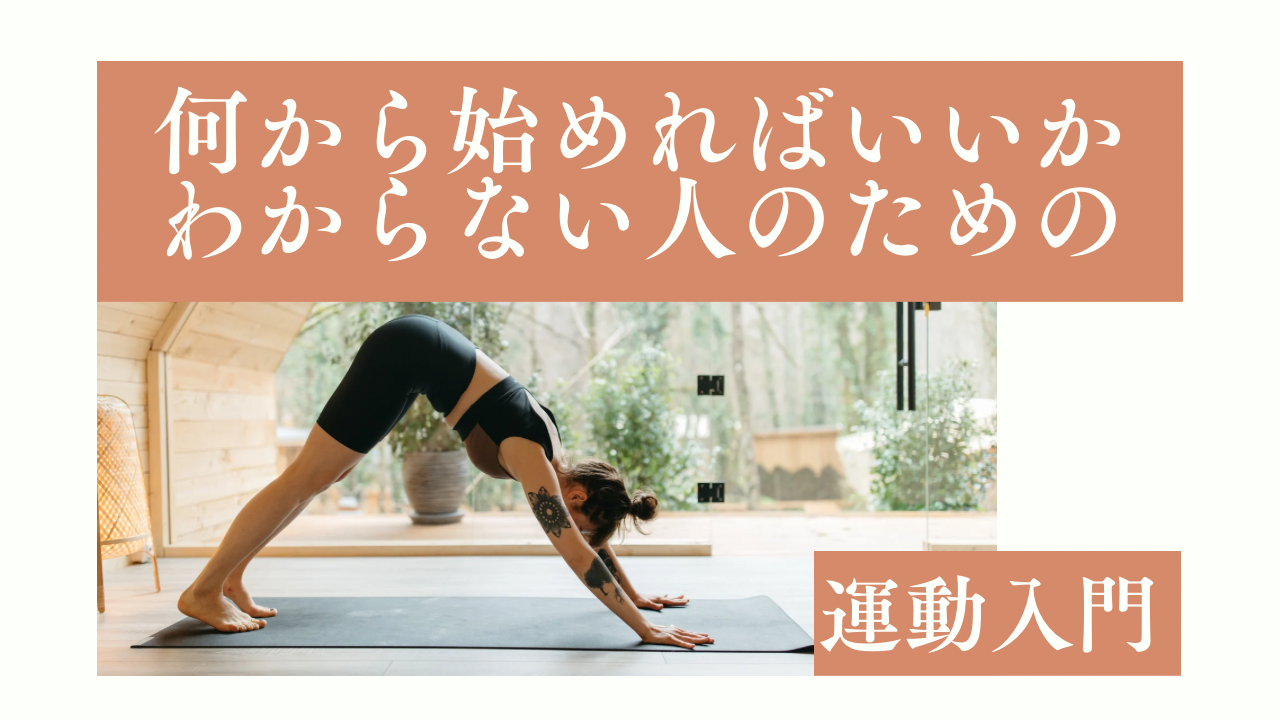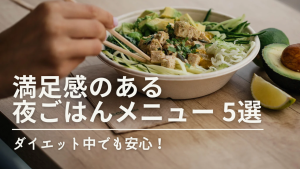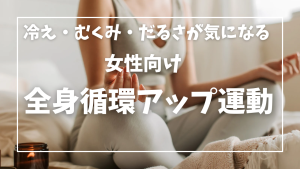「運動を始めたいけれど、何から手をつけていいかわからない」「ジムに行くのは敷居が高い」「運動経験がないから不安」…このような悩みを抱えている方は非常に多いのではないでしょうか。健康のために運動が大切だとわかっていても、具体的にどこから始めればよいのか迷ってしまうのは当然のことです。
運動を始めることは、決して難しいことではありません。特別な技術や高価な器具、ジムの会員権も必要ありません。大切なのは、自分の現在の体力レベルを正しく把握し、無理のない範囲から少しずつ始めることです。
この記事では、運動初心者の方が安全で効果的に運動習慣を身につけるための完全ガイドをお届けします。体力チェックから具体的な運動メニュー、継続のコツまで、今日から始められる実践的な内容を、医学的根拠に基づいて詳しく解説します。
この記事をご覧いただいている方へ。
この記事をご覧いただいている皆さまは、健康面に気を使い、食生活や運動習慣の見直し、フィットネスジムに通われている。もしくは、入会等をご検討されている健康意識の高い方々ではないでしょうか?
実際に、厚生労働省が、健康づくりのための身体活動基準・指針を作成し、生活習慣病予防のための運動を推進しています。
また、日本政策金融公庫が発表した消費者動向調査(令和3年7月)では、運動面や食に関する志向で、“健康志向”の方が多く年々と増加しています。
より皆様が、健康的で充実した人生を歩めるよう、誠意を込めて記事を執筆いたしましたので、どうか最後までご覧ください。
<その他資料>
※スポーツ庁の資料(新型コロナウイルス感染症の流行による国民のスポーツへの参画状況や意識の変化、健康状態等に関する調査研究(令和2年度))では、コロナ終息後のパーソナルトレーニングジムの利用者数は急増中。
※経済産業省の『特定サービス産業動態統計速報』の結果でも、フィットネスジム並びに、パーソナルジム利用者は数多くいらっしゃいます。
【PR】BEYOND

BEYONDは全国120店舗以上を展開する、BEST GYM AWARD受賞のパーソナルジム。美ボディコンテストでの入賞者や資格をもつ、プロのパーソナルトレーナーのみが揃っております。
過度な食事制限やトレーニングなく、ライフスタイルに合わせて無理なく継続できます。
コースは大きく以下3つにわかれているため、目的に合ったトレーニングを選択可能です。
| 料金(税込) ※最小プランの場合 | 内容 | おすすめ | |
| ライフプランニングコース | 月々18,500~ ※323,664円 | パーソナルトレーニング 食事管理 サプリメント | 目標がある方向け |
| 回数券コース | 月々4,700円~ ※102,300円 | パーソナルトレーニング ストレッチ | 継続したい方向け |
※当社指定の信販会社を利用した際の分割料金となります。・10回券96,800円の場合:分割回数:24回/支払い期間:24ヶ月/手数料率:年利7.96%/支払い総額:115,850円
特に回数券コースの月々4,800円~は、業界内でも最安値級で良心的です。
BEYONDが気になる方は、まず無料体験トレーニングを活用してみてください。
\今なら入会金50,000円が無料/
なぜ運動が必要なのか?現代人の健康課題
運動を始める前に、なぜ運動が必要なのかを正しく理解することが重要です。現代社会が抱える健康課題と、運動がもたらす効果について詳しく見ていきましょう。
現代人の運動不足の実態
現代社会では、多くの人が深刻な運動不足に陥っています。
- 座位時間の増加:デスクワークの普及により、日本人の平均座位時間は1日約7時間に達し、世界最長レベルです。
- 日常活動の減少:車や電車の利用、エレベーターの普及により、日常生活での身体活動が大幅に減少しています。
- 運動習慣の低下:週2回以上運動する人の割合は、成人男性で33.4%、成人女性で25.1%にとどまっています。
- 体力の低下:20-64歳の体力は、過去20年間で継続的に低下傾向にあります。
運動不足が引き起こす健康問題
運動不足は様々な健康問題の原因となります。
- 生活習慣病:糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満などのリスクが大幅に増加します。
- 筋力低下:30歳以降、年間約1%ずつ筋肉量が減少し、日常生活に支障をきたします。
- 骨密度の低下:骨粗鬆症のリスクが高まり、転倒による骨折の危険性が増加します。
- 精神的な問題:うつ病、不安障害、ストレス関連疾患のリスクが高まります。
- 認知機能の低下:認知症のリスクが増加し、記憶力や判断力が低下します。
世界保健機関(WHO)によると、運動不足は世界の死亡原因の第4位を占め、年間約320万人の死亡に関連しています。一方で、定期的な身体活動により、心疾患のリスクを30%、糖尿病のリスクを27%、認知症のリスクを30%減少させることができます。
運動がもたらす健康効果
適切な運動は、身体的・精神的健康に多大な効果をもたらします 。
- 心肺機能の向上:心臓や肺の機能が向上し、日常生活での疲労感が軽減されます。
- 筋力・筋持久力の向上:筋肉量が増加し、基礎代謝が向上します。
- 骨密度の維持・向上:骨を強くし、骨折リスクを減少させます。
- 免疫機能の向上:適度な運動により免疫力が向上し、感染症にかかりにくくなります。
- 精神的健康の改善:ストレス軽減、気分の向上、睡眠の質の改善が期待できます。
運動を始める前の準備:現状把握と目標設定
効果的で安全な運動を始めるためには、まず自分の現在の状態を正しく把握し、適切な目標を設定することが重要です。
健康状態のチェック
運動を始める前に、必ず健康状態をチェックしましょう。
- 医師への相談:持病がある方、40歳以上の方、長期間運動をしていない方は、運動開始前に医師に相談することをお勧めします。
- 血圧測定:安静時血圧が140/90mmHg以上の場合は、医師の指導の下で運動を開始します。
- 心拍数の確認:安静時心拍数を測定し、運動中の目標心拍数を設定する基準とします。
- 既往歴の確認:心疾患、糖尿病、関節疾患などの既往歴がある場合は、特に注意が必要です。
体力レベルの評価
自分の現在の体力レベルを客観的に評価しましょう。
- 階段テスト:2階まで階段を上がって息切れの程度を確認します。息切れが激しい場合は、軽い運動から始めましょう。
- 歩行テスト:普通の速度で10分間歩いて、疲労度や息切れの程度を評価します。
- 柔軟性チェック:前屈や肩の可動域をチェックし、関節の硬さを確認します。
- 筋力チェック:椅子からの立ち上がりや、壁での腕立て伏せができるかを確認します。
現実的な目標設定
継続可能な目標を設定することが成功の鍵です。
- SMART目標:具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限付き(Time-bound)な目標を設定します。
- 短期目標:「今週は3回、10分間歩く」など、1-2週間で達成できる小さな目標から始めます。
- 中期目標:「1ヶ月後には20分間続けて歩けるようになる」など、1-3ヶ月の目標を設定します。
- 長期目標:「半年後には週3回、30分間の運動を継続する」など、3-6ヶ月の目標を設定します。
超初心者向け:今日から始められる簡単運動
運動経験がほとんどない方でも、今日から安全に始められる簡単な運動をご紹介します。特別な器具や場所は必要ありません。
日常生活の中でできる運動
まずは日常生活の中で体を動かす機会を増やしましょう。
- 階段の利用:エレベーターやエスカレーターではなく、階段を使うようにします。最初は1-2階分から始めましょう。
- 歩く距離を増やす:一駅手前で降りて歩く、駐車場の遠い場所に車を停めるなど、歩く機会を意識的に増やします。
- 家事を運動に:掃除機をかける、洗濯物を干す、庭の手入れなど、家事を積極的に行います。
- 立つ時間を増やす:テレビを見る時間の一部を立って過ごす、デスクワーク中に定期的に立ち上がるなど、座位時間を減らします。
室内でできる基本運動
天候に左右されず、自宅で安全にできる基本運動です。
- その場足踏み:テレビを見ながら、音楽を聴きながら、その場で足踏みをします。5分から始めて、徐々に時間を延ばしましょう。
- 椅子を使った運動:椅子に座ったまま、または椅子を支えにして、安全に運動できます。椅子からの立ち座りを10回繰り返すだけでも効果的です。
- 壁腕立て伏せ:壁に手をついて行う腕立て伏せです。膝をついた腕立て伏せよりもさらに負荷が軽く、初心者に最適です。
- ストレッチ:首、肩、腰、脚の簡単なストレッチから始めます。痛みを感じない範囲で、ゆっくりと行いましょう。
1週間の運動スケジュール例
超初心者向けの1週間の運動スケジュール例をご紹介します。
- 月曜日:5分間のその場足踏み + 5分間のストレッチ
- 火曜日:10分間の近所散歩
- 水曜日:椅子を使った運動10回 + ストレッチ5分
- 木曜日:休息日(軽いストレッチのみ)
- 金曜日:10分間のその場足踏み
- 土曜日:15分間の散歩
- 日曜日:好きな運動を自由に(または休息日)
初心者向け:基本的な運動プログラム
超初心者段階を卒業したら、より体系的な運動プログラムに取り組みましょう。
有酸素運動の基本
心肺機能向上と脂肪燃焼に効果的な有酸素運動から始めましょう。
- ウォーキング:最も安全で継続しやすい有酸素運動です。週3回、20-30分から始めて、徐々に時間と頻度を増やします。
- 室内有酸素運動:その場でのマーチング、軽いダンス、踏み台昇降など、室内でできる有酸素運動も効果的です。
- 水中ウォーキング:関節への負担が少なく、浮力により安全に行えます。プールが利用できる方にはお勧めです。
- サイクリング:膝への負担が少なく、楽しみながら続けられます。エアロバイクでも同様の効果が得られます。
筋力トレーニングの基本
筋力維持・向上のための基本的な筋力トレーニングです。
- スクワット:椅子を後ろに置いて、座るような動作でスクワットを行います。10回×2セットから始めましょう。
- 腕立て伏せ:壁腕立て伏せから始めて、慣れてきたら膝をついた腕立て伏せに進みます。
- プランク:体幹を鍛える基本的な運動です。最初は10-15秒から始めて、徐々に時間を延ばします。
- ランジ:片足を前に出して膝を曲げる運動です。バランスを取るために壁や椅子を支えにしても構いません。
柔軟性向上のストレッチ
関節の可動域を維持・向上させるストレッチです。
- 首のストレッチ:ゆっくりと首を左右、前後に動かします。各方向20秒ずつ行いましょう。
- 肩のストレッチ:肩を回す、腕を胸の前で伸ばすなど、肩周りの筋肉をほぐします。
- 腰のストレッチ:膝を胸に引き寄せる、腰をひねるなど、腰部の柔軟性を向上させます。
- 脚のストレッチ:ふくらはぎ、太ももの前後、股関節周りのストレッチを行います。
運動の種類と選び方
様々な運動の特徴を理解し、自分に合った運動を選ぶことが継続の鍵です。
有酸素運動の種類と特徴
心肺機能向上に効果的な有酸素運動の種類をご紹介します。
- ウォーキング:最も手軽で安全。膝や腰への負担が少なく、年齢を問わず始められます。
- ジョギング:ウォーキングより運動強度が高く、短時間で効果が得られます。ただし、関節への負担も大きくなります。
- 水泳・水中ウォーキング:全身運動で、関節への負担が最も少ない運動です。
- サイクリング:下半身中心の運動で、膝への負担が少なく、長時間続けやすい運動です。
- ダンス:音楽に合わせて楽しく運動でき、社会性も保てます。
筋力トレーニングの種類と特徴
筋力向上に効果的なトレーニングの種類です。
- 自重トレーニング:自分の体重を負荷として使う運動。器具が不要で、自宅で安全に行えます。
- ダンベル・バンド:軽い負荷から始められ、段階的に強度を上げられます。
- マシントレーニング:ジムのマシンを使用。正しいフォームで安全に行えますが、費用がかかります。
- 機能的トレーニング:日常生活の動作に近い運動で、実用的な筋力を向上させます。
柔軟性・バランス運動の種類
関節の可動域とバランス能力を向上させる運動です。
- 静的ストレッチ:筋肉をゆっくりと伸ばし、その状態を維持するストレッチです。
- 動的ストレッチ:関節を動かしながら行うストレッチで、運動前のウォーミングアップに適しています。
- ヨガ:柔軟性、筋力、バランス、精神的リラクゼーションを同時に得られます。
- 太極拳:ゆっくりとした動作でバランス能力と筋力を向上させ、転倒予防に効果的です。
継続するためのコツと習慣化の方法
運動を継続するためには、モチベーションの維持と習慣化が重要です。
習慣化のための環境づくり
- 時間の固定:毎日同じ時間に運動することで、生活リズムに組み込みます。
- 場所の確保:自宅に運動スペースを確保し、いつでも運動できる環境を作ります。
- 服装の準備:運動用の服装を前日に準備し、すぐに始められる状態にします。
- 器具の準備:必要最小限の運動器具(ヨガマット、軽いダンベルなど)を準備します。
モチベーション維持の方法
- 記録をつける:運動内容、時間、体調の変化を記録し、進歩を視覚化します。
- 小さな目標設定:達成しやすい小さな目標を設定し、達成感を積み重ねます。
- 仲間を作る:家族や友人と一緒に運動することで、お互いに励まし合います。
- 報酬システム:目標達成時の小さな報酬を設定し、継続の動機とします。
挫折を防ぐ心構え
- 完璧主義を避ける:100%完璧を目指さず、80%できれば良しとする柔軟な考え方を持ちます。
- 失敗を学習機会と捉える:うまくいかない日があっても、それを学習の機会として前向きに捉えます。
- 段階的な進歩:急激な変化を求めず、少しずつの進歩を大切にします。
- 楽しさを重視:義務感ではなく、楽しみながら運動することを心がけます。
よくある質問と解決策
運動初心者が抱きがちな疑問と、その解決策をご紹介します。
時間に関する悩み
- Q: 忙しくて運動する時間がありません A: 1日10分から始めましょう。通勤時間を利用した歩行や、テレビを見ながらのストレッチなど、隙間時間を活用できます。
- Q: どのくらいの頻度で運動すればよいですか? A: 週2-3回から始めて、慣れてきたら週4-5回に増やします。毎日少しずつでも構いません。
体力・健康に関する悩み
- Q: 体力がなくて続けられるか不安です A: 現在の体力レベルに合わせて、無理のない範囲から始めましょう。徐々に体力は向上します。
- Q: 持病があっても運動できますか? A: 医師に相談の上、適切な運動を選択しましょう。多くの場合、適度な運動は病気の改善に役立ちます。
効果に関する悩み
- Q: どのくらいで効果が現れますか? A: 体調の改善は2-4週間、体力向上は4-8週間、体型の変化は8-12週間程度で実感できることが多いです。
- Q: 運動しても体重が減りません A: 体重減少には食事管理も重要です。また、筋肉量が増えると体重は変わらなくても体脂肪は減少している可能性があります。
安全に運動するための注意点
怪我を防ぎ、安全に運動を続けるための重要な注意点をご紹介します。
運動前後のケア
- ウォーミングアップ:運動前には5-10分の軽い運動で体を温めます。
- クールダウン:運動後には5-10分のストレッチで筋肉をほぐします。
- 水分補給:運動前後と運動中の適切な水分補給を心がけます。
- 適切な服装:動きやすく、汗を吸収する服装と、足に合った運動靴を着用します。
体調管理
- 体調チェック:運動前に体調を確認し、体調不良時は無理をしません。
- 疲労の蓄積:過度な疲労を感じた時は、休息を取ることも重要です。
- 痛みへの対応:運動中に痛みを感じたら即座に中止し、必要に応じて医師に相談します。
- 睡眠の確保:十分な睡眠を取り、体の回復を促進します。
環境への配慮
- 天候の確認:悪天候時は無理をせず、室内運動に切り替えます。
- 時間帯の選択:交通量の少ない時間帯や、安全な場所を選んで運動します。
- 熱中症対策:夏場は涼しい時間帯を選び、こまめな水分補給を行います。
- 防寒対策:冬場は適切な防寒対策を行い、ウォーミングアップを十分に行います。
まとめ:今日から始める健康への第一歩
運動を始めることは、決して難しいことではありません。大切なのは、完璧を求めすぎず、自分のペースで少しずつ始めることです。今日から始められる小さな一歩が、やがて大きな健康改善につながります。
運動は「やらなければならないもの」ではなく、「自分の健康と幸せのために選択するもの」です。無理をせず、楽しみながら、自分に合った方法で続けることが最も重要です。
今日から始めてみませんか?まずは5分間のその場足踏みと、簡単なストレッチから。その小さな一歩が、あなたの健康で活動的な未来への大きな一歩となるはずです。
運動習慣は、一生の財産となります。今日始めた運動が、10年後、20年後のあなたの健康を支えてくれるでしょう。何から始めればよいかわからなかった方も、この記事を参考に、ぜひ今日から新しい健康習慣をスタートしてください。あなたの健康で充実した人生を応援しています。